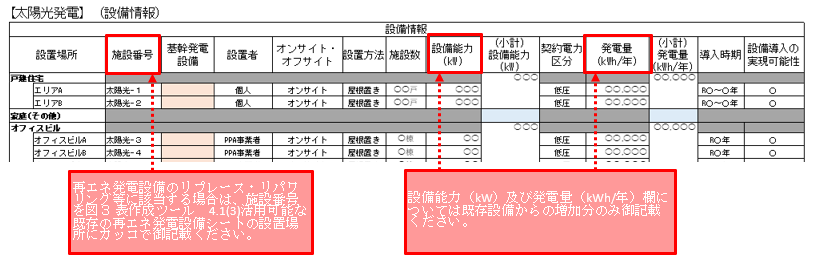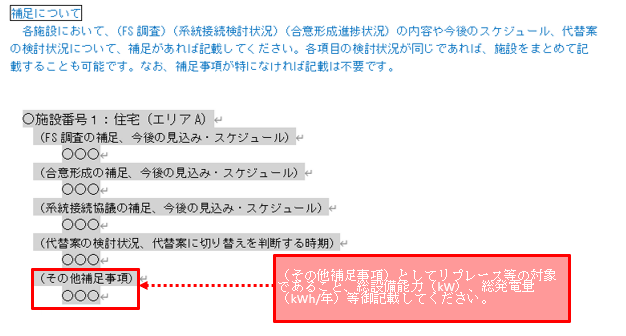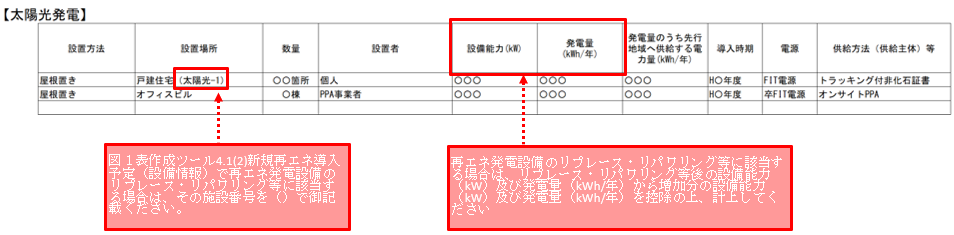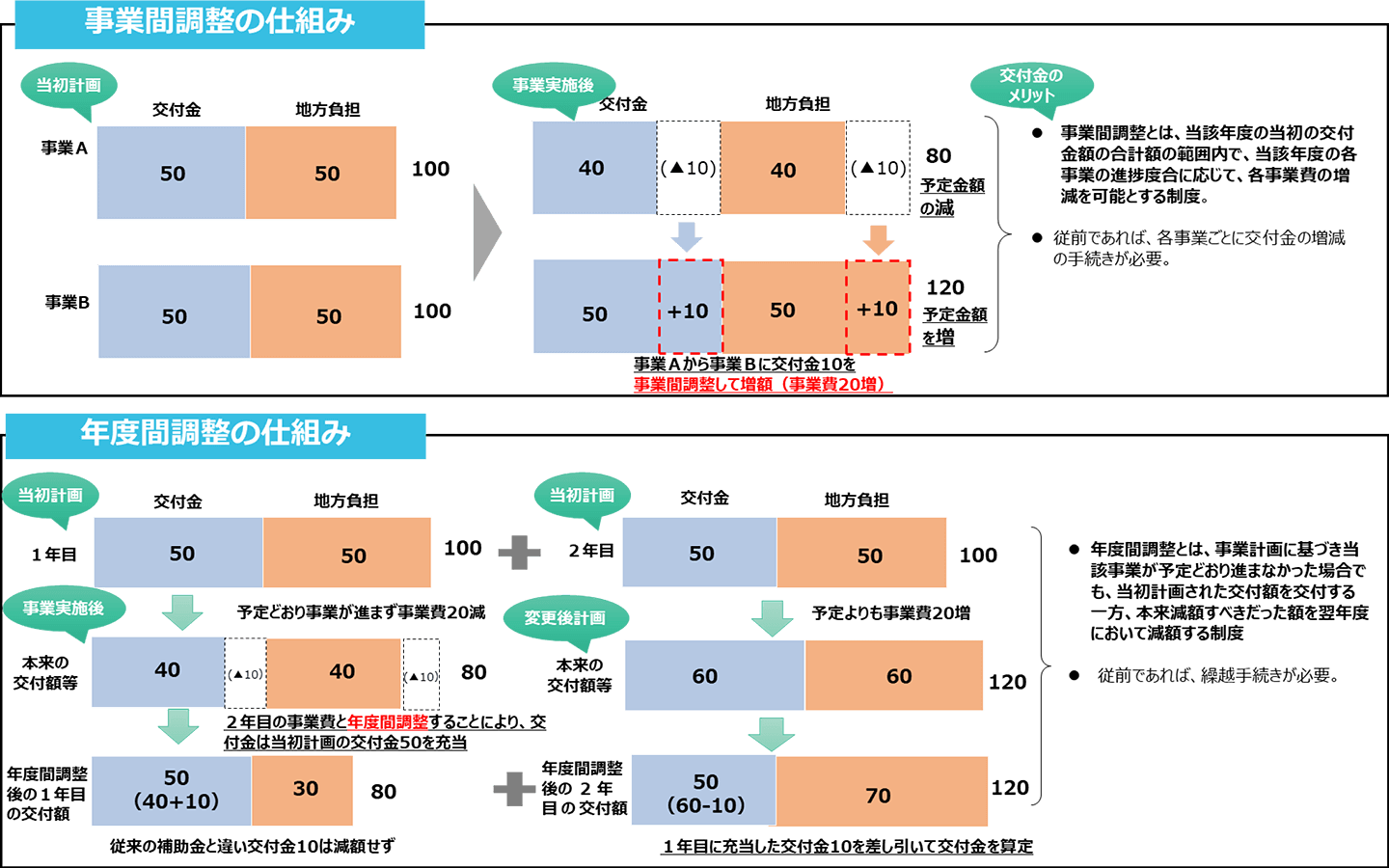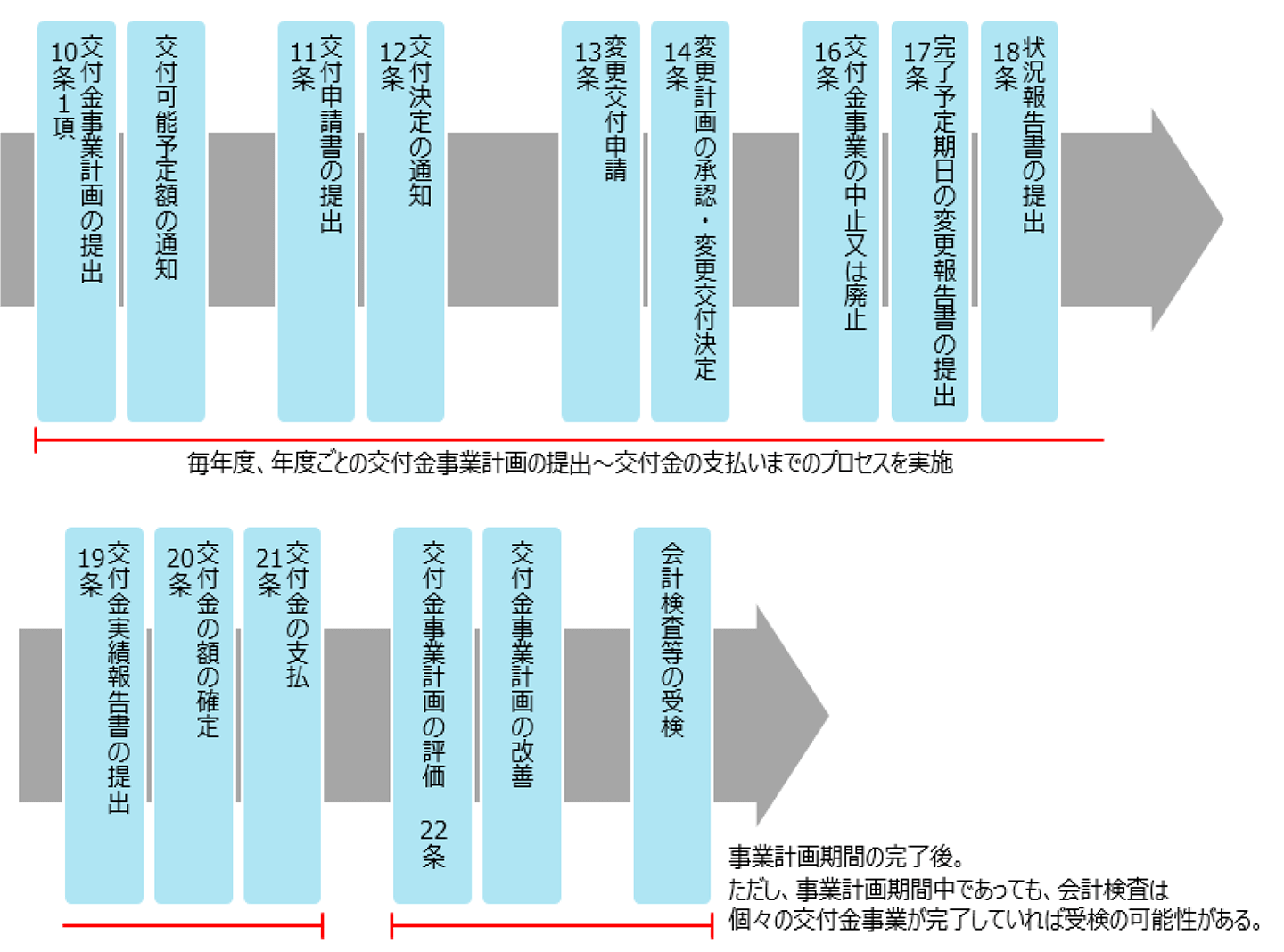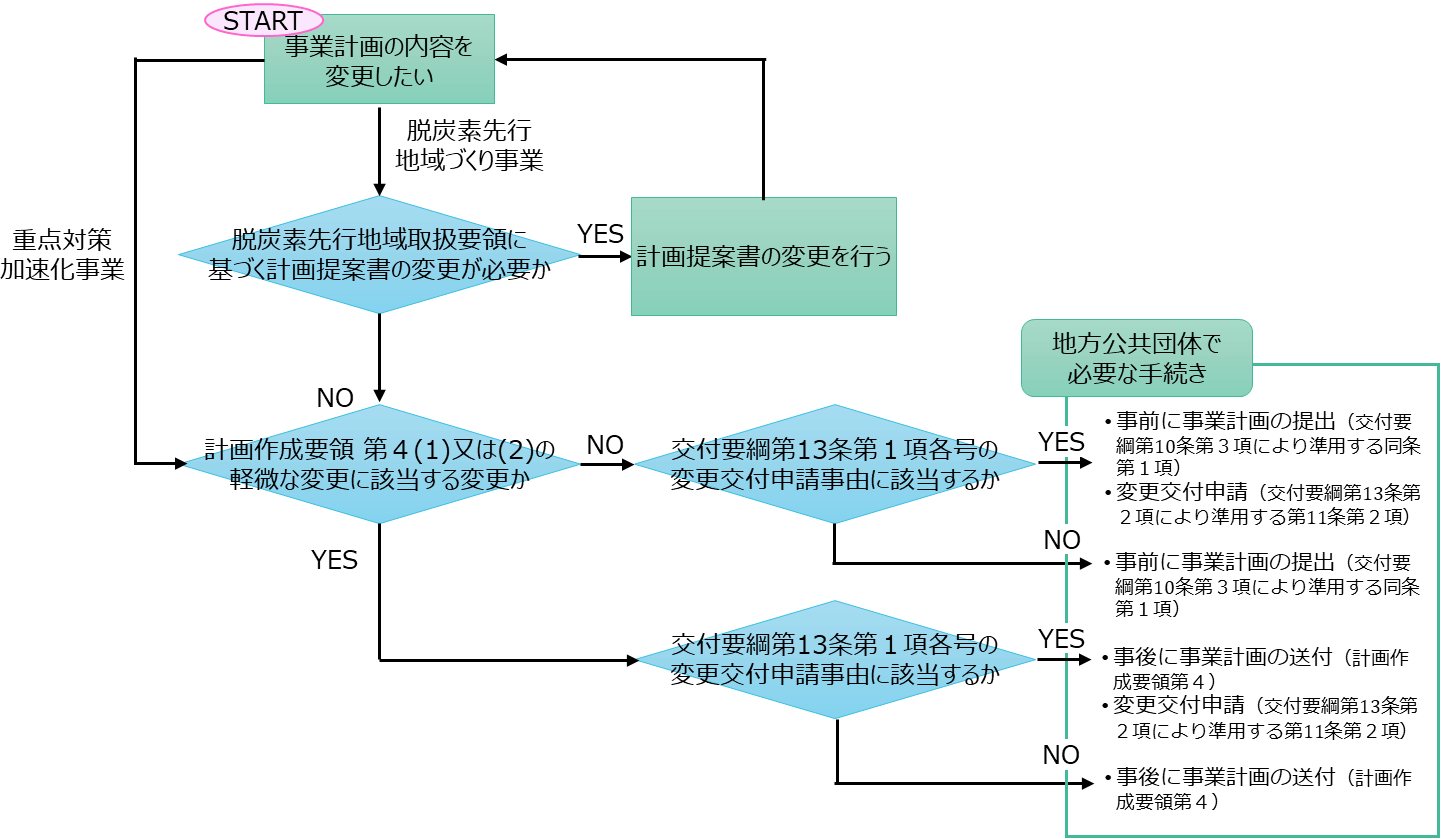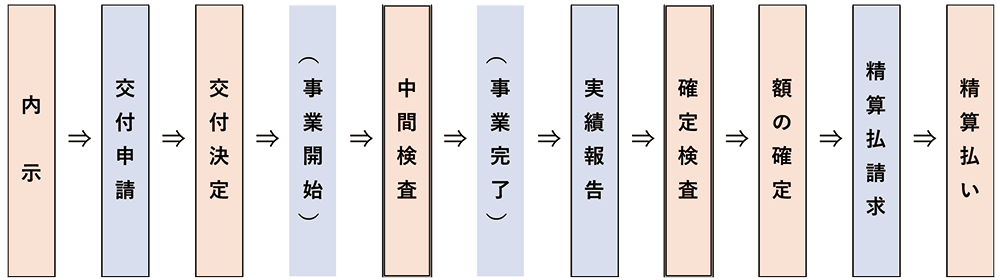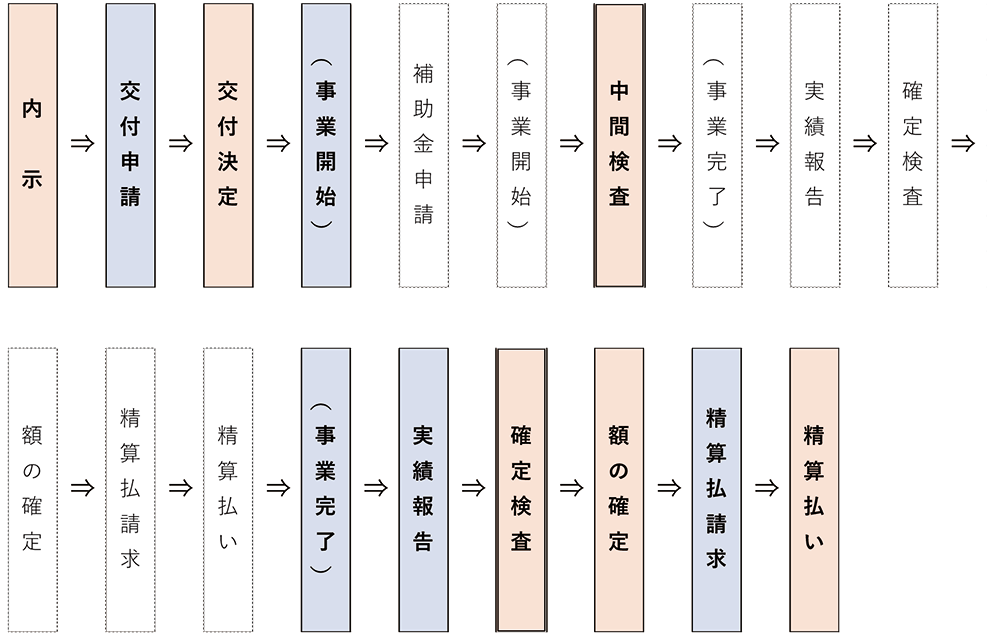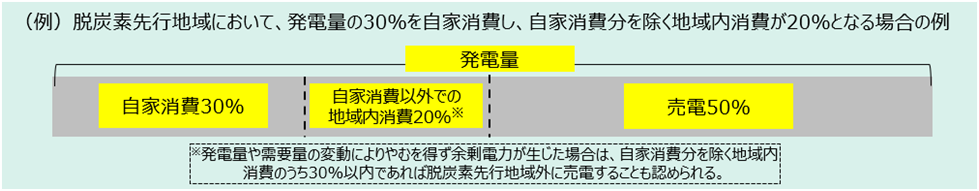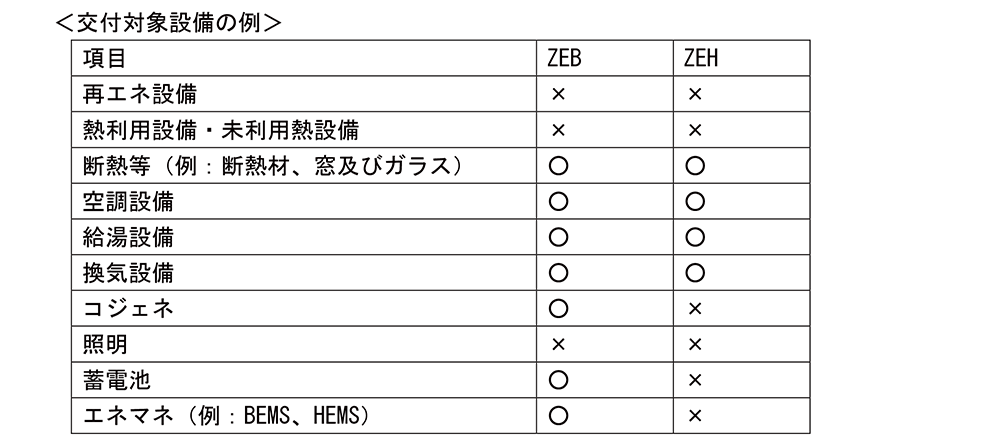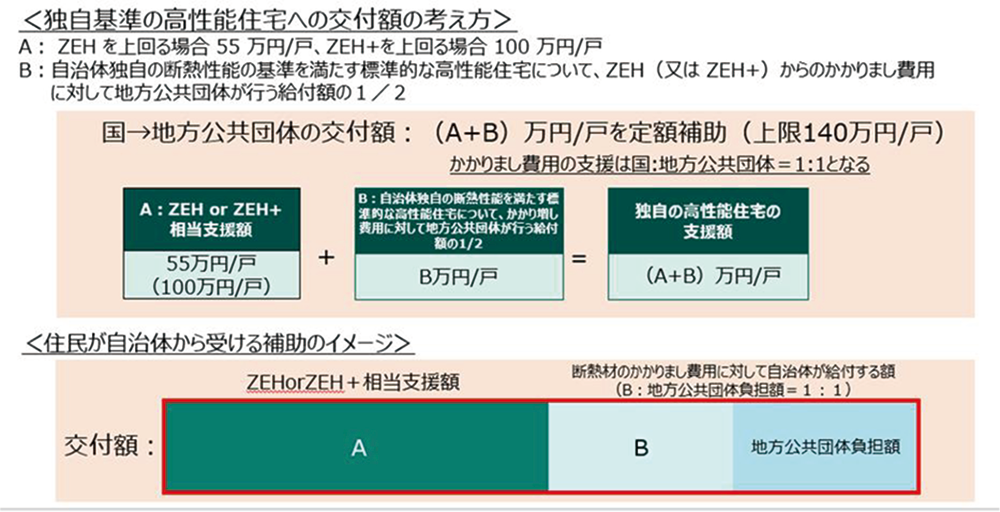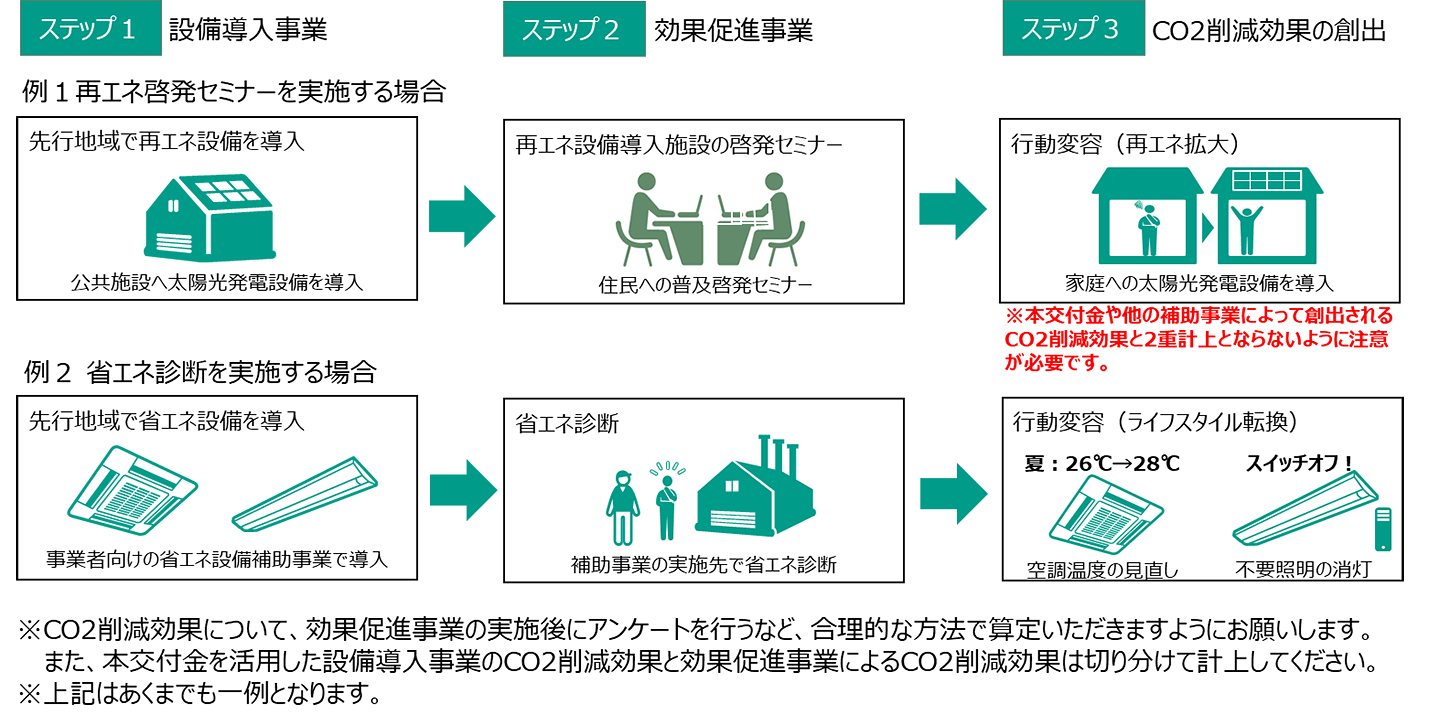問8. 脱炭素先行地域の範囲の特定について
「既存の区画等に沿い合理的な脱炭素先行地域の範囲が特定されていること」とは何か。
質問「脱炭素先行地域の範囲の特定について」に対しての


既存の区画等に沿った合理的な範囲とは、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域で構成した対象地域、基本戦略や個別計画に基づくエリアであること等が必須となります。また、複数エリアや、一定のエリアの外の施設を付加的に対象地域とする場合についても、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえて、脱炭素先行地域外も含めた地域全体の地域課題解決及び民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロに貢献するように設定していただくことが求められます。地域課題解決の観点では、例えば、旧市街地をバランスよく入れるといったものは、合理的な理由とみなさず、評価しません。エネルギーの観点では、例えば、一括的にエネルギーマネジメントを実施することで再エネの効率的な活用とコスト削減に取り組む等の説明が必須であり、単に同一の小売電気事業者が複数エリアにおいて電力供給を行っているという理由は認められません。
問9.脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制について
「脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制」とは何か。
質問「脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制について」に対しての


地方公共団体は、共同提案者に過度に依存することなく主体的に事業を進めるように、事業執行体制を構築することが必須です。2030年までに残された期間が短くなっていることから、より厳格に確認するようにします。
脱炭素先行地域に選定された後、事業を確実に実施することができるよう、新しい部署の新設や、人員拡充等を検討するほか、関係部署と調整・連携して取組を進める体制を構築することが重要です。
問10. 複層的な進捗管理評価の体制について
「外部有識者等を含む複層的な進捗管理・評価の体制」とは何か。
質問「複層的な進捗管理評価の体制について」に対しての


計画を選定地方公共団体が中心となって自律的に推進していくには、第三者の視点を含めて、状況を把握、評価を行い、計画をブラッシュアップしていくことが不可欠です。
そのため、計画実現のための実行計画の策定、地方公共団体内部における管理体制、外部の有識者等を含む委員会、市民意見の採り入れなど、複層的に管理・評価できる体制を整える必要があります。
問11. 事務事業編における目標について
「事務事業編では政府目標(50%削減)以上の目標」を設定することとあり、個別の措置についても、政府実行計画に準じた措置となっていることとあるが、「準じた」とは、どのように解釈すればよいか。
質問「事務事業編における目標について」に対しての


事務事業編については、地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し率先的な取組を行うことにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべきであることから、原則として政府実行計画の目標(2013 年度比 50%削減)を踏まえた野心的な目標を定めることが望ましく、特に、他の地方公共団体に先駆けて脱炭素に取り組もうとする脱炭素先行地域の提案地方公共団体は、率先して50%以上の目標を設定してください。
個別措置においても、原則は政府実行計画に応じた措置を実施していただきますが、廃棄物処理事業や上下水道事業など、温室効果ガスの排出量の多い施設等を保有する提案地方公共団体も想定され、これら施設等の規模や増減等の状況も踏まえて目標を設定することが重要であり、「準じた」としました。そのため、事務事業編の目標としてはそれらの特定の施設等を除いて「50%削減以上」とした上で、特定の施設については、「温室効果ガス総排出量に与える影響の大きい施設等の増減、事務・事業の動向を踏まえ、最大限の水準とすること」とし、該当性については個別に判断させていただく予定です。
問12. 事務事業編及び区域施策編の目標に対する進捗報告について
地方公共団体実行計画(事務事業編)に係る各取組等の進捗状況や、地方公共団体実行計画(区域施策編)に係る各施策等の進捗状況を報告する必要があるのか。
質問「事務事業編及び区域施策編の目標に対する進捗報告について」に対しての


主たる提案者である地方自治体と共同提案者となる地方公共団体は地方公共団体実行計画(事務事業編)に係る各取組等の進捗状況や、地方公共団体実行計画(区域施策編)に係る各施策等の進捗状況については、毎年度環境省に報告をしていただきます。また、その結果については環境省のホームぺージ等で公表します。
問13. 共同提案者となる地方公共団体による事務事業編及び区域施策編の目標設定について
共同提案者となる地方公共団体は主たる提案者である地方自治体同様に要件(0)前提となる事項のうち、事務事業編及び区域施策編の策定又は改定、目標設定に関する事項を満たす必要があるのか。
質問「共同提案者となる地方公共団体は主たる提案者である地方自治体同様に要件(0)前提となる事項のうち、事務事業編及び区域施策編の策定又は改定、目標設定に関する事項を満たす必要があるのか。」に対しての


共同提案者となる地方公共団体は、主たる提案者である地方公共団体同様に地方公共団体実行計画の事務事業編及び区域施策編について、以下の要件(0)前提となる事項における確認事項を満たすことが必須となります。
①地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)に即して、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)及び地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定又は改定していること。ただし、策定又は改定がなされていない場合は、令和7年度中に実施するスケジュールを示していること
②地方公共団体実行計画(事務事業編)の目標が、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(政府実行計画:令和3年10月22日閣議決定)の目標(2013年度を基準として、2030年度までに50%削減)以上になっていること(※)。また、個別の措置についても、政府実行計画に準じた措置になっていること
(※)温室効果ガス総排出量に与える影響の大きい施設等の規模やその増減、事務・事業の動向を踏まえ、これら施設等に係る目標についても最大限の水準とすること
③地方公共団体実行計画(区域施策編)の目標が、地球温暖化対策計画の目標(2030年度に2013年度から46%削減)にとどまらない野心的な水準(※)であること
(※)民生部門やその他の部門・分野について、地球温暖化対策計画の目標・目安を踏まえ、最大限の水準で設定をすること
問14. 先進性・モデル性の評価について
「既選定の脱炭素先行地域での取組と差別化され、優れている点が示されていること」とは何か。
質問「先進性・モデル性の評価について」に対しての


問15. 先進性・モデル性の該当数の考え方について
要件(1)先進性・モデル性では、類型表に当てはまる数が多い方が評価されるのか。
質問「先進性・モデル性の該当数の考え方について」に対しての


取組が多いだけで、評価することはありません。
計画提案書では、各地域の地域課題や地域特性を踏まえた、提案の中で主となる取組を記載するようにしてください。
問16. 大規模に事業を実施することの先進性・モデル性について
既選定の提案と比較し、大規模に事業を実施した場合、先進性・モデル性がある取組として評価されるのか。
質問「大規模に事業を実施することの先進性・モデル性について」に対しての


規模の大きさのみで、先進性・モデル性のある取組として評価することはありません。
問17. 脱炭素先行地域で活用する技術について
「脱炭素先行地域で活用する技術」について、「技術の導入効果を最大化するための導入方法や運用方法等における工夫について、既選定の脱炭素先行地域での取組と差別化され、優れていること」の具体例を教えてほしい。また、今後革新が期待される技術を盛り込むことは可能か。
質問「脱炭素先行地域で活用する技術について」に対しての


地域脱炭素ロードマップでは、地域脱炭素のキーメッセージとして「今ある技術で取り組める」ことを掲げていることから、脱炭素先行地域においては、実証段階の技術の導入は評価しません。また、地域脱炭素推進交付金の交付対象は「整備する設備は、商用化され、導入実績があるもの」となりますので御注意ください。
ペロブスカイト等、実証技術の実装化を図る取組が含まれている場合は、評価の中で考慮されることになりますが、この場合、実証関連予算等を活用するなど、地域脱炭素推進交付金とは別途財源を確保するとともに、当該実証技術の代替手段も併せて検討することが必要です。
技術については、当該地域で導入又は実施することの意義や妥当性を明らかにした上で、地域の事業者が中心となって、設備の施工や維持管理、再エネ電力事業の運営等を行うとともに、他地域への展開も見据え、導入方法や運用方法等について工夫することが特に重要です。
問18. 都道府県との連携について
「地域脱炭素の基盤創出」における「都道府県との連携」については、都道府県が主たる提案者または共同提案者として参画することが前提となるのか。
質問「都道府県との連携について」に対しての


都道府県が責任をもって積極的に取り組むことを期待し、その立場を担保するためにも、都道府県が主たる提案者又は共同提案者になることを想定しています。
脱炭素先行地域の取組を横展開させる観点からも、都道府県との連携が重要となっています。
問19. 個別KPIについて
個別KPIはどのように設定すればよいのか。
質問「KPIについて」に対しての


個別KPIは、その取組による効果の度合いを適切に評価するための重要な指標となります。そのため、要件(2)地域経済循環への貢献に係る確認事項においては、脱炭素先行地域の取組を通じて解決していくことを目指す課題とそれに向けた取組、また、そのための個別KPIが適切に設定されるとともに、個別KPIの改善に係る根拠や方法が適切に説明されていることが必要です。
取組を通じて得られる地域経済効果や防災効果、暮らしの質の向上などに係る効果を適切に評価できる指標で、過度に高い目標ではなく、実現可能な範囲の意欲的な目標を設定することが重要です。
問20. 地域経済循環に資する取組について
「地域経済循環に資する取組」とは、何か。
質問「地域経済循環に資する取組について」に対しての


地域脱炭素の取組は、産業、暮らし、交通、公共等のあらゆる分野で、地域の強みを生かして地方創生に寄与するように進められることが重要です。
例えば、地域で利用するエネルギーの大半は、輸入される化石資源に依存している中、再エネ導入を地域裨益型で行う必要があり、地域の企業や地方公共団体が中心になって、地域の雇用や資本を活用しつつ、地域資源である豊富な再エネポテンシャルを有効利用することが、地域の経済収支の改善につながると期待されます。
そうした中で、以下の5つの観点で、取組の効果が大きく、また実現可能なものとなるよう、検討いただくことが重要です。その効果の算出効果等が確認できないものは評価しません。
(観点)
①エネルギー代金の域内還流
②地域経済、地域雇用の創出・拡大
③地域資源の最大限活用
④地元事業者・人材の育成
⑤事業収益の還元
各観点の詳細については、「脱炭素先行地域づくりガイドブック(第6版)」を御参照ください。
問21. 事業継続性の確保、コスト低減の検討について
「事業を効率的かつ継続的に行う工夫が示されていること」とは、何か。
質問「事業継続性の確保、コスト低減の検討について」に対しての


脱炭素先行地域は、「『実行の』脱炭素ドミノ」の起点となり、取組を横展開していくことが期待されていることから、安易に国費に頼らない仕組み作りが重要です。
例えば、事業コストを低減させるため、資機材や燃料の調達コストを共同調達により低減する取組や、事業導入に当たって既存インフラを活用する取組、廃棄していたものを燃料に活用する取組等が考えられます。
その他、資金面の観点から、安易に国費に頼らず、民間からの出資や、住宅や民間施設において地域脱炭素推進交付金の高い補助率を一般の国庫補助金並みに抑える対応、ふるさと納税の活用等の工夫があげられます。
問22. 国費に安易に頼らない方策を講ずるべき経費の範囲について
「事業を効率的かつ継続的に行う工夫が具体的、定量的に示され、横展開の可能性等の観点も含め、地域脱炭素推進交付金等の国費に安易に頼らない方策が優れていること」とあるが、初期投資も含めて工夫する必要があるか。
質問「国費に安易に頼らない方策を講ずるべき経費の範囲について」に対しての


脱炭素先行地域は、取組の横展開が期待されていることから、初期投資も含めて、地域脱炭素推進交付金等の国費に安易に頼らない方策を検討することが、重要です。
なお、ランニングコストについては、地域脱炭素推進交付金の対象外です。
問23. 電力需要量の規模について
「電力需要量の規模が適切であること」の目安はあるのか。
質問「電力需要量の規模について」に対しての


2030年度までの残期間を踏まえ、民生部門電力及び民生部門電力以外の両取組ともに規模の大きさを追求するのではなく、先進性・モデル性や取組の実現可能性をより高めていただくことが重要との観点から、民生部門の電力需要量の規模については適切であることを評価することとしています。
各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、既選定の計画等を参考に適切な規模を確保していただきたいと考えています。
問24. 主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について
「民生部門の電力需要量の規模が適切であること」について、「脱炭素先行地域の主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について、公共施設は、これらの電力需要量を50%割り引き、民間施設は、一定のモデル性が認められない限り、これらの電力需要量を25%割り引いて評価する。」とあるが、なぜそのような評価をするのか。また、民間施設における「一定のモデル性」とはどのようなものか。
質問「主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について」に対しての


具体的に範囲を特定し、当該範囲内の民生部門電力需要家の全てを対象とすることが基本的な考え方であるため、この考え方に則らず付加された施設の需要量を割り引くこととしました。なお、民間施設については、公共施設と比較して合意形成等がより困難であることを考慮し、公共施設より小さな割引率としています。
「一定のモデル性」については、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえ、当該地域を対象とするエネルギーに関する観点での合理的な理由が必要です。例えば、一括的にエネルギーマネジメントを実施することで再エネの効率な活用とコスト削減に取り組む等の説明が必須となります。
問25. 地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量の割引について
「脱炭素先行地域の主として取組を実施する範囲内外にかかわらず、地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量は、電力需要量を100%割り引いて評価する。」のはなぜか。
質問「地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量の割引について」に対しての


地方公共団体の所有する廃棄物処理施設については、自家消費による一定規模の需要量が見込まれるとともにそれ以上の発電量も確保でき、CO2排出量実質ゼロも期待できることから、新規再エネ設備の導入における調整等を行わなくとも大規模な需要量の上積みが可能です。
これを他の施設の需要量と同等に評価すると、廃棄物処理施設の有無で、電力需要量確保の観点で差が出てしまうことから、地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量については、100%割り引くこととします。
一方で、民間事業者の廃棄物処理施設とその発電設備に関しては、計画への参加の合意形成等が、より困難であることを考慮し、割り引かず、100%の需要量で評価することとします。
問26. 再エネの地産地消について
「脱炭素先行地域内の民生部門の電力需要量に占める当該脱炭素先行地域のある地方公共団体内で発電する再エネ電力量の割合(地産地消率)を、可能な限り高くすること」とあるが、その目安はあるのか。
また、複数の地方公共団体(市区町村)で提案する場合や都道府県が提案する場合、どの範囲を地産地消とみなせるのか。
質問「再エネの地産地消について」に対しての


脱炭素先行地域の趣旨を踏まえれば、取組の成果が地域に裨益し、エネルギー代金の循環や雇用創出等により地域経済循環に資することから、地産地消率を最大限向上させるよう、御検討ください。
また、複数の地方公共団体(市区町村)で提案する場合や都道府県が提案する場合については、以下の範囲をそれぞれ地産地消とみなします。
①市区町村が、その他の市区町村と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村内の再エネ電源も地産地消の範囲となります。
②市区町村が、その他の市区町村及びそれらの管轄の都道府県と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村内の再エネ電源の地産地消の範囲は①と同様です。都道府県が設置する再エネ電源についても、地産地消の範囲は主たる提案者である市区町村及び共同提案者である市区町村内に設置された再エネ電源が地産地消の対象になります。
③都道府県が主たる提案者となり、管内の市区町村と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村以外の当該都道府県内の再エネ電源についても地産地消の対象となります。
※地域脱炭素推進交付金を活用し、脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を当該再エネ発電設備と同一市区町村内の脱炭素先行地域内の需要家(脱炭素先行地域の提案者が都道府県の場合は同一都道府県内の当該脱炭素先行地域内の需要家)に限定する必要があることに留意してください。
※2問6記載の複数の「主たる提案者」が提案する場合は、上記①又は②を準用する。
問27. FIT及びFIPについて
再エネ等の電力供給量について、地方公共団体内にFIT売電の再エネ発電施設がある場合、脱炭素先行地域内での電源活用の有無によって、評価に影響はあるか。
また、FIPにより調達した再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。
質問「FIT及びFIPについて」に対しての


FIT売電の再エネ発電設備で発電した再エネ電力を、脱炭素先行地域内の対象施設に供給することは可能ですが、環境価値が切り離されているため、別に環境価値を買い戻し、付加した状態で供給する必要があります。
FIP(Feed-in-Premium)制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。
問28. 民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の規模について
「温室効果ガス削減の規模が適切であること」とあるが、その目安はあるのか。また、評価事項において「複数組み合わせて実施していること」とあるが、どのような取組でも評価されると考えて良いのか。
質問「促民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の規模について」に対しての


2030年度までに残された期間を踏まえ、民生部門電力及び民生部門電力以外の両取組ともに規模の大きさを追求するのではなく、先進性・モデル性や取組の実現可能性をより高めていただくことが重要との観点から、民生部門電力以外の取組における温室効果ガス削減の規模については適切であることを評価することとしています。
各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、既選定の計画等を参考に適切な規模を確保していただきたいと考えています。
一方で、脱炭素先行地域として、多分野にわたり温室効果ガス排出量を総合的に削減することが期待されることから、単独の取組に限らず、複数の取組の実施に向け、各地方公共団体の地域特性や地域課題に応じて積極的に御検討ください。
また、「組み合わせて実施する」とは、複数の取組を別々に実施した場合より、あわせて実施することで相乗効果が見られ、地域の課題解決が見られる等、相乗効果が認められる場合、「組み合わせて実施していること」として評価します。
なお、温室効果ガスの削減効果やその算定根拠(排出係数、原単位など引用した出典名の記載を含む)については必ず示すようにしてください。
問29. EVの温室効果ガス削減について
ガソリン車のEVへの切り替えは、全て温室効果ガス排出削減の対象となるのか。また、車両の導入だけでなく、EV充電スタンドの設置のみは対象となるのか。
質問「EVの温室効果ガス削減について」に対しての


EVへの切替えによる温室効果ガス排出削減の効果は、該当車両の導入前後のエネルギー(燃料)の使用に伴う温室効果ガス排出量を比較して算出した上で、トータルで導入後の排出量が削減されていることが重要です。そのため、EVに供給される電力を再エネ電力とすること等が必要です。
なお、EV充電スタンドの設置は単なる電力供給の手段であることから、温室効果ガス削減効果は認めておりません。
問30. 吸収源対策の活用について
吸収源対策の活用は、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の取組に含まれるのか。
質問「吸収源対策の活用について」に対しての


吸収源対策の活用は、温室効果ガス排出量削減量の算定方法が、確立されている場合に限り、民生部門以外の温室効果ガス排出量削減の取組として、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の対象になります。
例えば、森林吸収源対策やバイオ炭の活用は、吸収量やその算定根拠(引用した出典名の記載を含む)が示されれば対象になり得ます。
なお、温室効果ガス排出量削減量の算定方法が、確立されている場合であっても、脱炭素先行地域の取組と関係なく、従前から実施されているものについては、評価の対象外となりますので御注意ください。
問31. 廃棄物発電の位置付けについて
廃棄物発電による再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。
質問「廃棄物発電の位置付けについて」に対しての


廃棄物発電により得られた電力のうち、バイオマス発電に相当する分については、既存の廃棄物発電も含めて再エネの電力供給量に算入することができます(前項のとおり、FITの場合は、小売電気事業者等から環境価値が付加された状態の電力のみを算入できます。FIP制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。)。
バイオマス発電に相当する発電量については、廃棄物発電量に、バイオマス比率(焼却対象ごみの組成調査結果等により把握されたプラスチックの割合を除いたもの)を乗じることで把握することができます。
プラスチックの割合に応じた発電量分については、「再エネ発電量」として評価しませんが、「再エネ等」に含まれるものとし、証書によるオフセットと同等の評価として扱います。
ただし、プラスチックの焼却により非エネルギー起源CO2の排出を伴うため、脱炭素先行地域にプラスチックの割合に該当する発電量を供給する場合には、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の民生部門電力以外における取組において、当該供給量と同程度の排出削減を推奨します。
問32. 再エネ賦存量調査の対象範囲について
再エネ賦存量調査は、地方公共団体全域又は脱炭素先行地域内のみのどちらを対象とするのか。
質問「再エネ賦存量調査の対象範囲について」に対しての


地方公共団体全域における再エネポテンシャルを踏まえ、追加的な再エネ導入量を把握した上で、脱炭素先行地域の取組を実施する範囲を設定することが望ましいことから、当該地方公共団体の全域を対象として調査いただくようお願いします。
問33. 再エネ賦存量を確認する対象について
再エネ賦存量の確認は、「地域特性に応じ」とあるが、都市部であれば太陽光のみとする等、地域の特性に応じた再エネ種のみを対象とすれば良いか。網羅的な記載が必要か。
質問「再エネ賦存量を確認する対象について」に対しての


地域の特性により、明らかに想定されない再エネ種については、ポテンシャル把握の対象とする必要はありません。
問34. 需要家との合意形成について
電力需要家との合意形成について、脱炭素先行地域に応募するまでに、どの程度実施しておく必要があるのか。
また、合意形成の裏付けとして合意文書等の提出は必要か。
質問「需要家との合意形成について」に対しての


対象とする各需要家に対しては、脱炭素先行地域として実施する取組である旨と、地域脱炭素推進交付金は、脱炭素先行地域に選定されることが交付の条件である旨を明確に説明していただいた上で、合意形成を図っていただくことが必要です。
必要な合意形成のプロセスを検討し、合意を得るまでの道筋が明確で、その進捗度が高いほど、再エネへの切替えの見通しが立ち、円滑に事業が実施されると期待できることから、高く評価されます。
脱炭素先行地域選定後に「需要家へ説明する」、「実施するエリアを確定させる」、ということでは、2030年までの実行が求められる中、提案段階で関係者との合意形成の見通しが低いと判断せざるを得ません。なお、申請後の状況について、選定過程でお伺いする場合もありますので、御承知おきください。
また、計画提案書には各合意主体との合意形成の実施状況等について詳細に記載いただくこととしており、状況を説明するために特に必要と判断される場合、合意文書等、合意形成の状況を示す参考資料を提出いただいても構いません。
問35. 民生需要家を原則全て対象とすることについて
「脱炭素先行地域内の民生部門需要家を原則全て対象としていること」とあるが、例えば特定の業務に供される施設のみを対象とすることも、条件を満たさないのか。
質問「民生需要家を原則全て対象とすることについて」に対しての


要件(6)需要家・供給事業者・関係者との合意形成の確認事項のとおり、「脱炭素先行地域内の民生部門需要家を原則全て対象としていること」としています。そのため、指定した脱炭素先行地域のエリア内の一部の施設のみを対象とすることはできません。
問36. 関係者間における体制構築及び合意形成について
関係者間における体制が「具体的に」構築され、「適切に」合意形成が図られていることとはどういうことか。
質問「関係者間における体制構築及び合意形成について」に対しての


脱炭素先行地域の取組を実現するには、それを確実に実施する体制の構築が不可欠で、提案の時点での確度を示していただく必要があります。
計画に掲げる各取組に携わる再エネ発電等事業者、送配電事業者、地域エネルギー会社、熱供給事業者、運輸事業者、PPA事業者、地元企業、金融機関、大学等の教育機関、自治会、経済団体、農業団体等事業者が特定され、各事業者の役割を明確にし、合意形成が図られていることが必要です。
合意形成の在り方は様々ですが、必要に応じ、連携協定を締結したり、脱炭素先行地域推進のコンソーシアムを設立してメンバーに加わってもらったり、共同提案者となっていただく等も有効です。
「脱炭素先行地域づくりガイドブック(第6版)」に連携体制図等の具体例も記載しておりますので、御確認ください。
問37. 2030年以降の将来的な見通しを踏まえた適切な取組の考え方について
脱炭素先行地域は民生部門の電力消費に伴うCO2ゼロを2030年度までに実現するものであるが、脱炭素先行地域での取組が、2030年以降の現実的な将来見通し(人口減少や高齢化等)を踏まえた適切な取組となっていることとは、どのような考え方か。
質問「2030年以降の将来的な見通しを踏まえた適切な取組の考え方について」に対しての


脱炭素先行地域の取組は、単に電力契約を再エネメニューに切り替えるというだけでなく、再エネ発電設備やそれに付随するインフラ設備等を伴うものであり、それらの設備は、今後長期間にわたって利用されることが想定されます。
そのため、人口減少や産業構造の変化、施設の統廃合といった「厳しくも現実的な将来見通し」を踏まえた上で、脱炭素先行地域として脱炭素化に取り組む意義があるか、導入する再エネ発電設備等の場所・規模が適切か、それらのインフラが2030年以降も継続的に活用され、地域の発展に資するものであるかどうかを見極めることが重要です。